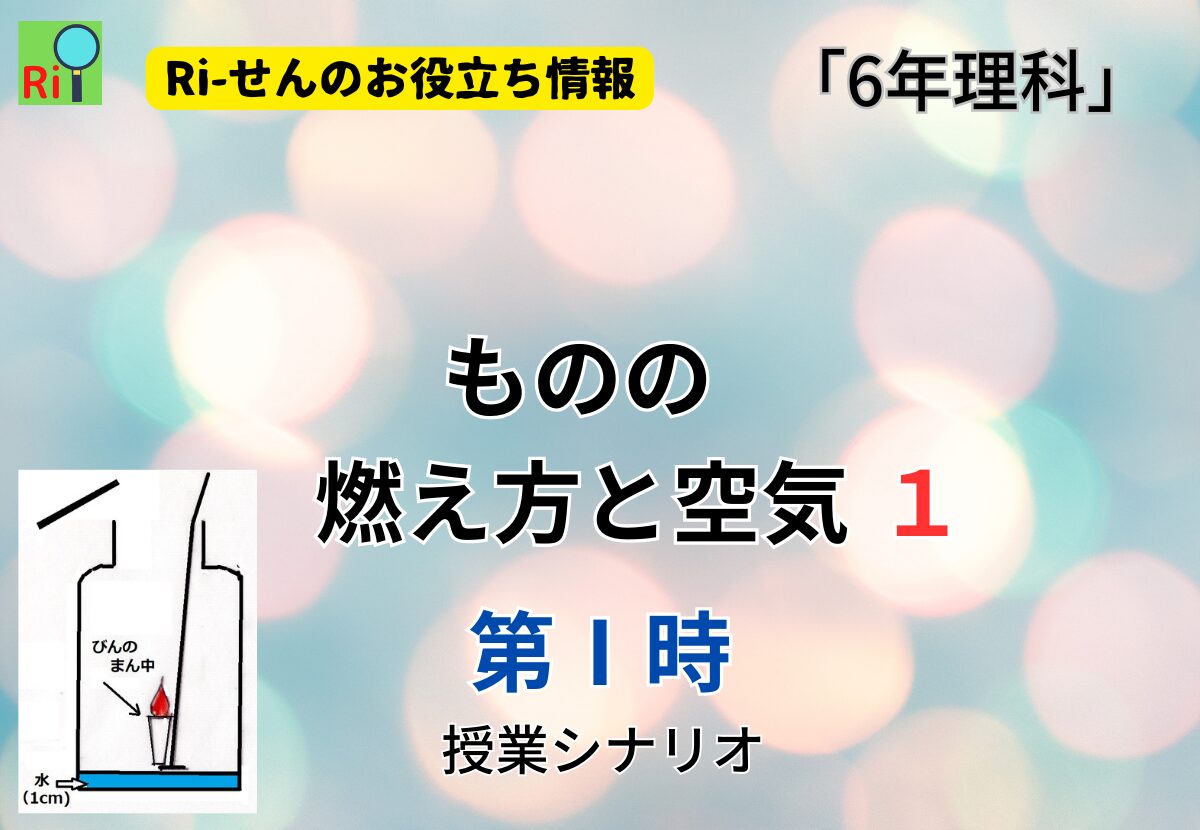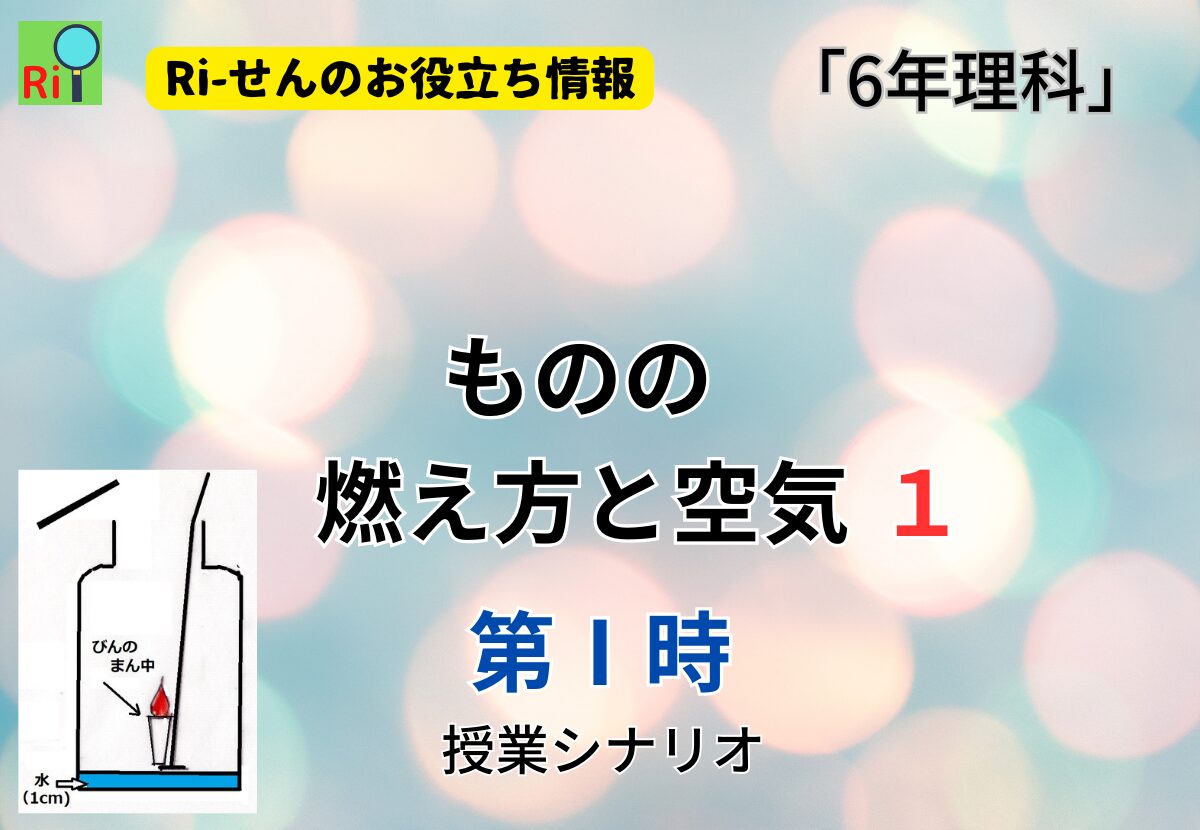理科の「授業開き」をどのように行ったのか、ご紹介します。
この記事は、コロナ禍が始まった2020年の授業を元に書き起こしたものです。
理科授業を担当することになった方のお役に立てたら幸いです。
「授業開き」という言葉に馴染みがない方もいらっしゃるかもしれません。
簡潔に言えば、その年度に初めて行う授業の事です。
学級担任ではない専科教員は、
始業式から三日後あたりに、「その日」がやってきます。
その授業は、全力で準備し臨まなければなりません。
この年は、自己紹介に続けて、
「理科でつける力」、「授業の進め方」、「成績」について話すことにしました。
「授業ノート」を用意し、教室で話すとおりに投げかけや指示を書いていきました。
話に関連する事柄についての調べ物は、すでに済ませておいてあります。
板書もシミュレーションし、流れをチェックして準備を終えました。
※お知らせ
このサイトは2025年8月末をもって閉じさせていただきます。
これまでの投稿ページは加除修正を加え順次「はてなブログ」へ移行させていきます。
(現在は、「理科の授業開き」のみ移行を完了しています)
今後、授業づくりに関する事などご興味がありましたら、こちらをお尋ねください。
click here 理科の授業開き – Ri-Senのお役立ち情報
1.本日の内容を板書する
授業が始まる前、子ども達はこう思っています。
こわい先生なのか、やさしい先生なのか。
やさしい先生だったらいいな。
先生は、どのような授業をするのだろうか。
楽しい授業だといいな。
どきどきだか、わくわくだかしています。


まだ休み時間ですが、ずんずんと教室に入っていきます。
何人かが、「理科の先生だ」などと言っています。
チョークを手に取り、黒板の左端に「本日の内容」と書き、
くるりと振り返って子ども達を見渡していると、変化が起こりだしました。
座り始めたのです。
授業の始まりを察したようです。
少しずつおしゃべりも収まって、チャイムが鳴りました。
この時点で子ども達は、もう授業者の手の平に乗っている、
そんな空気になりました。
板書しただけで「授業を受ける構え」が生まれました。


2.座席順に指す(全員に当てるようにする)
第一声は名乗ることから始まります。



今年度、みなさんの理科授業を担当します、理家野です。
自分の名前をさっと書きます。
続けてその隣に「41」と書き、問いかけました。
T:何の数でしょう?
一呼吸おいて「はい、〇〇さん。」と名前を呼び、
最前列の子どもを指しました。
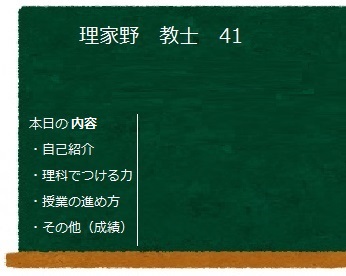
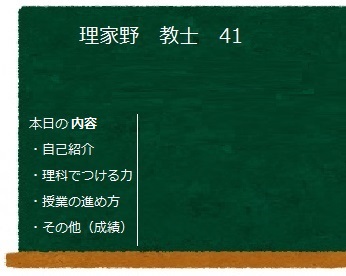


反応がありません。
いきなり指されて面食らっているようです。
「考え中のようですね。」
と言って隣を指します。 やはり、黙っています。
3人目も同様。 これは、まずい!
指される、と緊張するものです。(大人も同じです。)
急にスポットが当たり、みんなの視線が自分に集まったように感じます。
どきどきして、頭が真っ白になる。
その心境はよく分かります。
授業をする立場からすると、これを利用しない手はありません。
授業には適度な緊張感を持たせることが必要です。
指していくのが一番です。
しかし、このままではいけません。沈黙が続くのはよろしくありません。
3.分かりません、と言わせる
手を打たねばなりません。
子ども達には、このようなときの処し方を教えます。



分からないときは、「分かりません」と言いましょう。
投げかけられたら反応する。これはお約束です。
授業は、流れが大切。
流れとは「思考の流れ」のことです。
子どもからの反応が滞ると、このがプツリと切れてしまいます。
そうならないように、
教師とのやりとりの作法を初日に教えておくのです。
4.待たない
子どもが発言するまでじっと待つことはしません。
指名して(3秒くらいか)すぐに言葉が返ってこなければ、助け舟を出します。
その子にしてみれば運悪く教師から当てられ、みんなから注目されています。
思考停止状態。
そこから早く解放してあげなくてはいけません。



答えられない時は、「分からない」と言ってください。
「考え中」でもいいんですよ。あとから言うのもOKです。
みなさんは、分からないから学校へ来ているんです。
答えられないことがあっても当たり前。恥かしく思う事はありません。
空白をつくらない、ということです。大事にしたいのは、授業のテンポです。
5.何でも言える空気
最初の投げかけ、「41」という数は何なのか。
閃いたようです。さっと手が挙がりました。



「41」は、先生の年齢です!
この先生が41歳だって?!
発言した本人も、それを聞いた子ども達も絶対そうは思っていません。
言ってみただけでしょう。
本人(私)も「うれしい」とは思ってはいないのですが、満面の笑みで返します。



うれしいことを言ってくれますねぇ。
でも「41」は、年齢ではありません。
何を言ってもだいじょうぶ。そんな空気にしていきます。
子ども達は思いつくままに、あれこれ言って、やっと正解に辿り着きました。
「41」は私の経験年数でした。
40年も先生をやっているんだ、という空気になりました。
6.理科で付ける力
次に「64」と板書しました。
何の数なのか、同じように順番で言わせていきます。
これはすぐに分かりました。私の年齢でした。
3つ目に書いた数字は、「105」。
子ども達が1年間に受ける理科の授業時数です。
すぐに言い当てる子どもがいてびっくりしました。
その発言につなげて投げかけます。
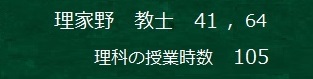
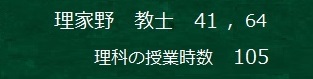



理科の授業は、1年間に105時間するように決められています。
その時間にみなさんが身につけるのは、どんな力でしょうか。
これはちょっと難しい。
誰も手を挙げないだろうなぁ・・・
と思っていると、答える子がいるから驚きました。しかも、的はずれではありません。
実は、
教科書の表紙をめくっていくと書かれているのです。それを見つけたのかもしれません。
その発言を少し補って、理科で身に付ける力を板書しました。
「問題を見つける」・「調べる」・「結果から考える」
この3つです。



実は、もう105時間はないのです。 なぜか分かりますね。
全員が叫ぶように言いました。 コロナウイルス!!と。
「新型コロナウイルス」 と板書します。
ここから「理科でつける力」の話を始めていきました。
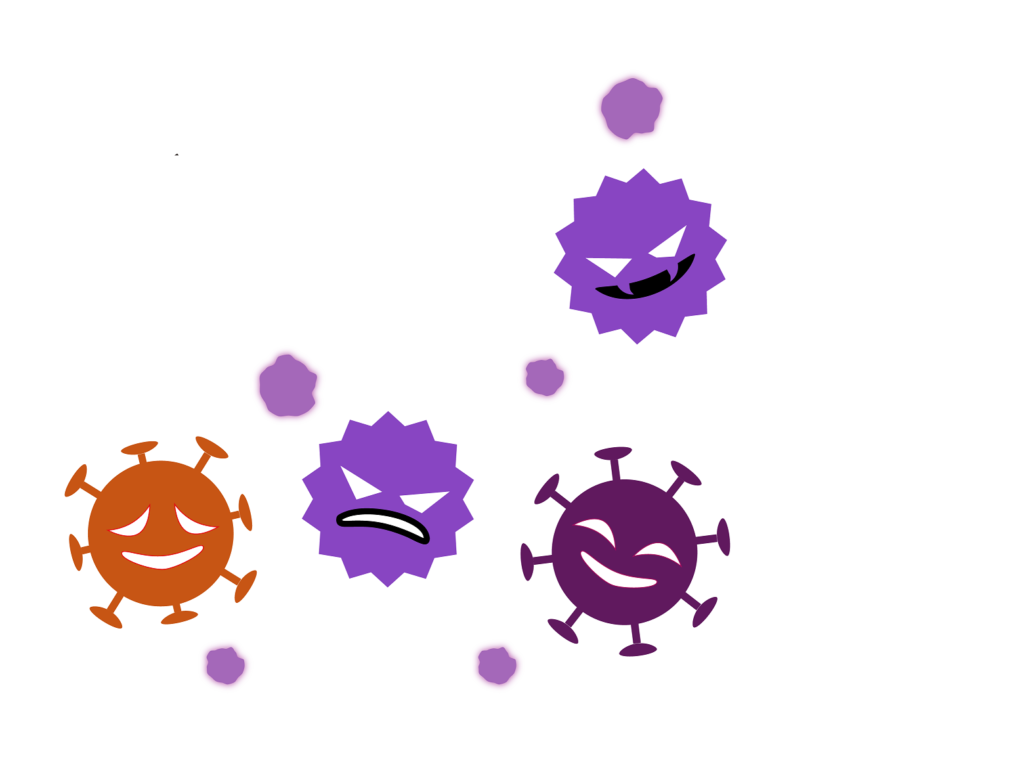
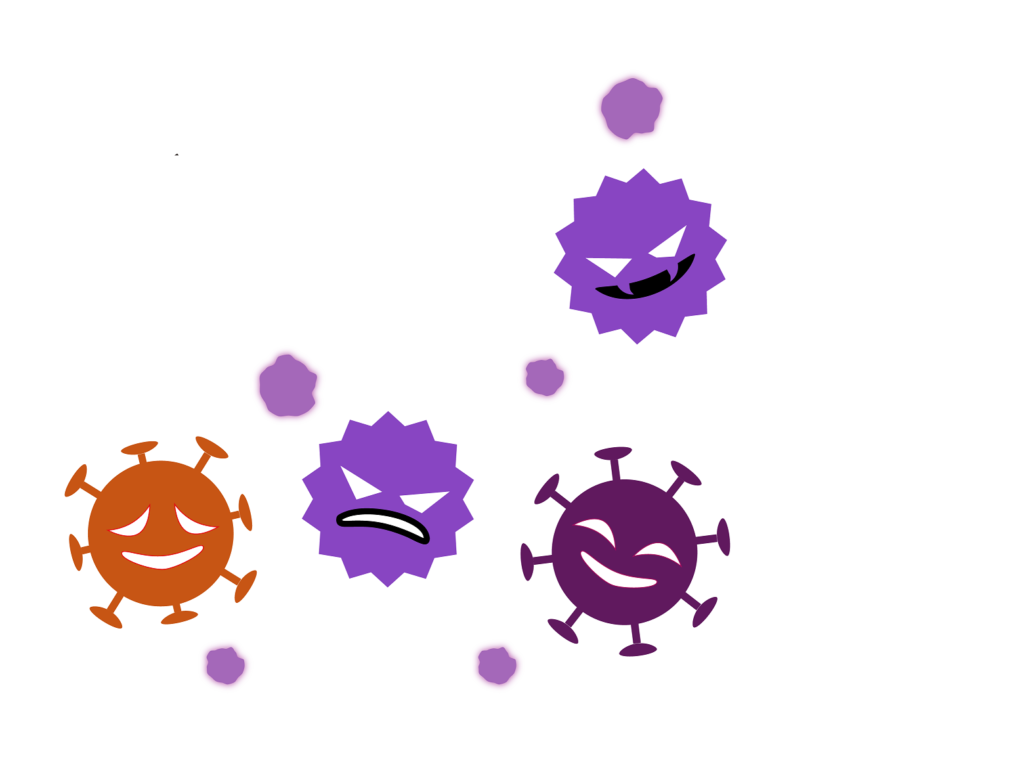
7.「問題を見つける」とは
「問題を見つける」とはどういうことか、「新型コロナウイルス」を例にします。



「新型コロナウイルス」
この言葉から、みなさんはどんな問題が浮かびますか?
分からないこと、知りたいこと、疑問に思うことは何でしょう。
考えたことを言ってもらい、それについて知っている子がいれば、答えてもらいます。
授業者(私)の役目は、ファシリテーター(司会者)です。
数人の手がぱっと挙がりました。
どんな病気なのか。
治す薬はあるのだろうか。
そう、そう。その調子。
いくつか発言が続くうちに「問題を見つける」とはそういうことか、とみんなも分かってきたようです。
が、出された疑問に答える子がいません。
子どものほとんどは、
世界的な規模でパンデミックの渦(禍)中にある「新型コロナウイルス」についてあまり知識がないのでした。
少しは学び合いの場になるのでは、と思っていましたが見込み違いでした。
4月から休校措置となって2か月あまり、
時間はあっても、疑問に思う事を進んで調べることはなかったようです。
最高学年の6年生ですが、そんなものかもしれません。
8.「初めて知る」を入れる
授業はもちろん、
朝会でもその他の活動でも「初めて」となる場を入れるよう心がけています。
へぇー、そうだったんだ
それは知らなかったなぁ
なるほど! そうやればできるのかぁ。
そういうことがあれば、子ども達は、学校に来てよかったと思うはずです。
学校に行けば、新しい何かが得られて楽しい、となります。
そのうきうきとした気持ちは、家に帰ってからの話題となっていくでしょう。
子ども達が「初めて知る」事は、授業準備をする中で浮かび上がってきます。
それは、自分(私)も知らなかったことです。
明日の授業が楽しみになってきます。
9.授業のシナリオをつくる
「新型コロナ」については、事前にできるだけ調べておきました。
子ども達から出るであろう問題を想定し、答えとともにノートにメモしていきます。
以下は、その一部です。
■ そもそも、「コロナ」とは何ですか
→ ウイルスの形が太陽光の環のように見えることから名づけられたのです。
■ なぜコロナの前に「新型」が付くのですか
→ 「コロナウイルス」は以前からあって、その新しい型が見つかったので「新型」がつくのです。
■ コロナウイルスの「ウイルス」とは何ですか
→ いきものの細胞の中に入って増える生物です。



その大きさは、0.002μmです。
μは「マイクロ」と読みます。1mmの 1000分の1が1μmです。



なんか、分かりにくいんですけど・・・



例えば、1mのものさしが1mmとするでしょう。
そのものさしの1mmの目盛りが1μmです。
ウイルスは、その500分の1の大きさなんだ。



うわー。目(肉眼)では、絶対見えないね。そんな大きさだったら
マスクやすき間を通り抜けちゃうんじゃないかなぁ。



マスクする効果はあるのかしら。ガーゼのマスクはあんまりなさそう。
感染防止のためのマスクの効果・選び方・注意点 | 健康長寿ネット (tyojyu.or.jp)
10.着地点へ
授業には、着地点があります。
子ども達の実態に合わせてばかりでは、もっていきたいところへ行きつきません。
そこで、こちらから投げかけ、話をしていきます。
理科という勉強が「わたしたちの生活」と密接につながっていることに気づかせたいわけです。
T:感染すると、どうなるのでしょう?
C1:死にます。外国で多くの人が亡くなっているニュースを見ました。
C2:重い肺炎になる人が多いそうです。その機械が足りないらしいです。
T:肺炎は、命にかかわる病気です。なぜか分かりますか。
肺は、呼吸に関わるものです。6月頃かな、勉強しますよ。
T:店に入るとき消毒の容器がおいてありますね。なぜ、シュッとやるのでしょう。
ウィルスは、アルコールによってすぐに死滅してしまいます。
店内で感染するのを防ぐためにしているのですね。
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
T:ワクチンを打つとは、どういうことでしょう。
治療するための注射だと思っている子どももいるようです。
免疫といい、その病気に罹らないか軽くて済む状態をつくりだすことと説明します。



「新型ウイルス」の予防ワクチンは、日本にはありません。
作れてないので外国から買うしかありません。
もしも、買えなかったら、売ってくれなかったらどうしましょう。
みなさんは、このことについてどう思いますか?



日本でもワクチンを作れるようにしないとダメです。
朝日新聞デジタル そもそもワクチンとはなに? 新型コロナワクチンの一番の特徴は? (asahi.com)
理科が私たちの生活とつながっていることに気づき始めたようです。
11.教科書の表紙
コロナウィルスの話から離れ、話題を変えます。
ここからは教科書を使います。
T:表紙を見ましょう。この人の名前は言えますよね?


C:キュリー夫人です。 引用:マリ・キュリー – Wikipedia より
T:そのとおりです。
「マリ・キュリー」と呼んだ方がいいと思いますが、教科書の案内キャラになってますね。
では、キュリー夫人について知っている事を言っていきましょう。
〇〇さんから、どうぞ。
この投げかけは、空振りでした。
「知りません」が続いてしまいました。伝記を読んでいないようです。
となれば、教師の出番です。
危険な放射性物質に晒されながら研究を続け、それががんの研究につながっている話をしました。
<参考> マリ・キュリーの業績
・放射線の研究、ノーベル賞(物理学、化学)2度の受賞。
・ラジウムの発見 放射能の単位「キュリー」(チェルノブイリ原発事故後、ベクレルが使われている)
・負傷者の為にレントゲン撮影車に乗り、治療に各地を回る。
・科学の発展の為、特許をとらず抽出した試料は化学者に分け与えた。
教科書を裏返して「科学者の言葉」を読んでいる子どもがいました。
よく気が付きましたね、とほめて各自で読むように指示しました。
キュリーの右の写真「ファラデー」は、今日の生活になくてはならない電気の研究をした人。
左下の「湯川博士」については
「実験がおもしろい」と言っていたこと、核廃絶に向けて平和運動に取り組んでいたことを話しました。
まとめに入ります。



ここまでで、
みなさんは理科という勉強についてどんなことを感じましたか?
理科、つまり科学ですが、
それが私たちの生活とつながっていて、とても大切ということが
少し分かってもらえたのではないかと思います。
1コマ目の授業は、ここで終了。
5分間の休憩の後、授業再開です。
なにしろ、初日にして2時間続きの理科授業の日なのでした。
2コマ目は、授業と評価について話をしてから、最初の単元に入る予定です。
12.授業で大切にしたいこと
5分のトイレ休憩をとり2コマ目を開始します。
本校ではチャイムは鳴りません。
席に着いていない子ども達がいますが、構わずに始めてしまいます。
スクリーンにツバメの写真を出します。(プロジェクターを使っています)
声をかけずとも、子ども達は座り出しました。
授業開始の号令を待ったりはしません。投げかけます。


T:ツバメを見かける季節ですね。
学校の昇降口あたりでも巣づくりが見られていますが、ここで問題です。
親ツバメは、どのようにヒナにエサを与えているでしょうか?



3択問題にしましょう。
A エサのやり方など、何も考えていない。
B 順番に、つまり公平にエサをやっていく。
C 欲しがって口を大きく開けているヒナにエサをやっていく。
子ども達に選ばせると、圧倒的にBでした。
公平にエサやりをする、というものですが、実際はCのようです。



自然界では、公平や平等ということはありません。
弱肉強食です。
私たち人間の世界でも、そのような面が見られますが、少なくとも
学校では「みんなで育つ」という考えを大切にしたいと先生は思います。
少し、具体的にして呼びかけました。
・声をかけあって学習を進めましょう。困っているお隣さんをほっといたらいけません。
・考えたことや分かったことを共有していきましょう。教え合うということです。
発明でも、ものづくりでも、何でも自分一人でやっていくことなどありません。
力を合わせたり、相談したりして進めています。
話を戻し、ツバメの子育てについて補足しておきます。
T:ところで、ツバメの子育ての話ですが、
エサをもらえないヒナはどんどん弱っていって死んでしまうように思われますが、
そんなことはありません。
親ツバメは、一日500回以上エサを運ぶそうです。
エサをもらい続けたヒナは、満腹になると食べなくなりますから、他のヒナはもらえるようになります。
心配いりません。自然はうまくできていますね。
13.実験・グループに関して
次に、「実験」について話をしていきます。
感染予防の観点から3蜜を避け、話し合いは必要最低限とします。
余計なおしゃべりはNG(no good)です。
実験は、終了していなくても、時間がきたら終了です。
(ですから、やり方をよく理解し手際よくしないといけません。)
実験には失敗がつきものであることも話します。
なぜうまくいかなかったか、それを考えること。
ノーベル賞になった研究も、身近な文具(例えば商品名ポストイット)等でも
失敗から始まっている話をしました。
実験グループは、こちら(教師側)で編成します。



実験や観察のグループは、担任と相談してこちらで決めます。
誰誰と同じグループだったらいいな、皆さんは思うでしょう。
その逆もありますね。
あの人とはなりたくないとか、話したくないとか、あるかな。
そういうのは年齢関係なくあるかもしれませんが、要は、
その人とどう折り合いをつけていくかです。
そんなことも、学校で勉強することの一つにしてください。
14.成績の話
学校では、市販のワークテストをつかっており、「通知表」作成の参考にします。
この学区の子ども達の多くが学習塾に行き、2,3割が私学進学を希望しています。
知識理解の観点の平均点は、90点台です。
高得点の子どもが多いので、
その数値のみをもって評定をしていくわけにはいきません。
ですから「テストの点数は参考です」と言っておきます。
100点満点も何度かとっているのに、なぜこの評定になるのか。
そんな説明を求められたことは一度もありませんが、
年度初めに評価・評定について説明をしておくわけです。



「あゆみ」の話をしておきましょう。
テストの点数だけで成績はつけられません。
知識面の平均が、95点以上なら◎がつく可能性はあります。
思考・判断・表現については、テストの点数のほか、ノートに実験結果や考察が適切に書かれているかを見るようにします。
主体的に学習しているかは、授業中の様子で判断します。
去年は、自作のテストを何度かしました。難しかったようです。
考えながら授業を受けていないと答えられない問題を出しました。
まだ少し、授業時間がありました。
実験器具(集気びん、燃焼さじ、燃えさし入れ等)を見せながら、その名称を問う活動をしました。
※次時の授業については、こちら ものの燃え方と空気 | Ri-せんのお役立ち情報 (ri-sen.com)
関連記事