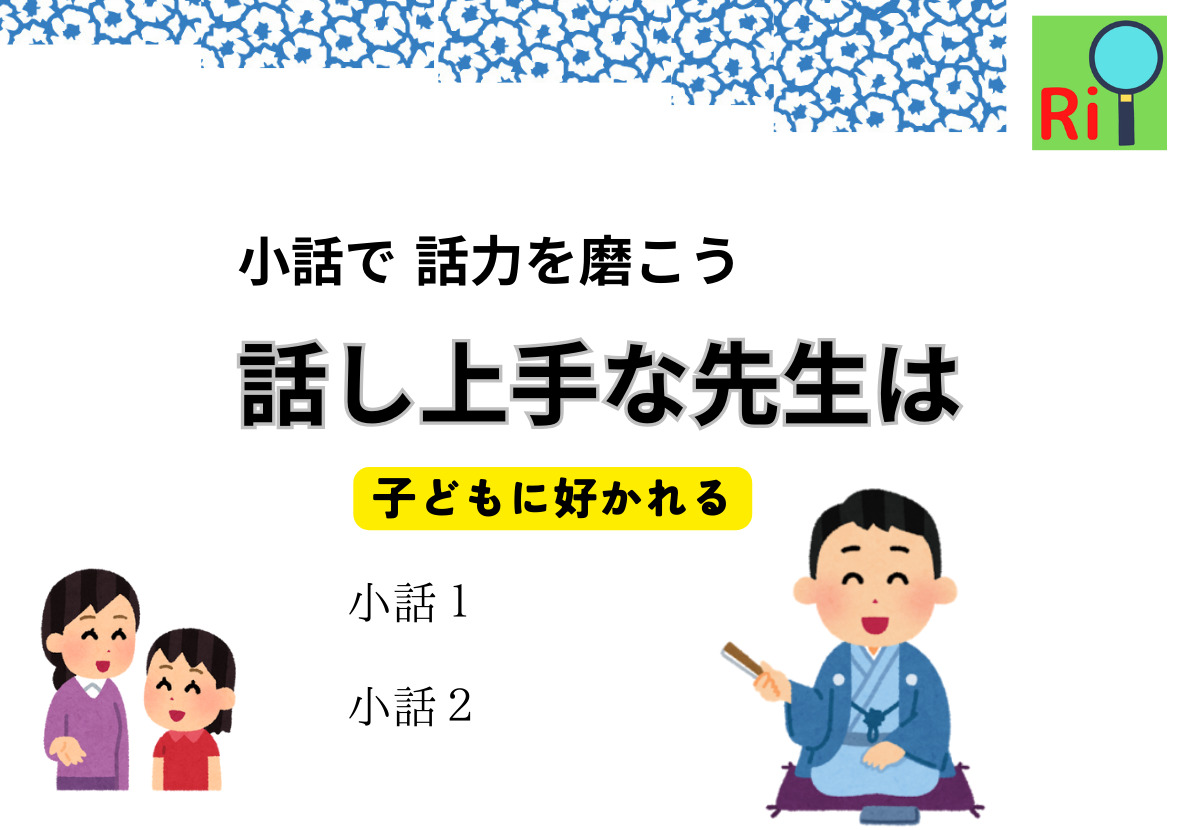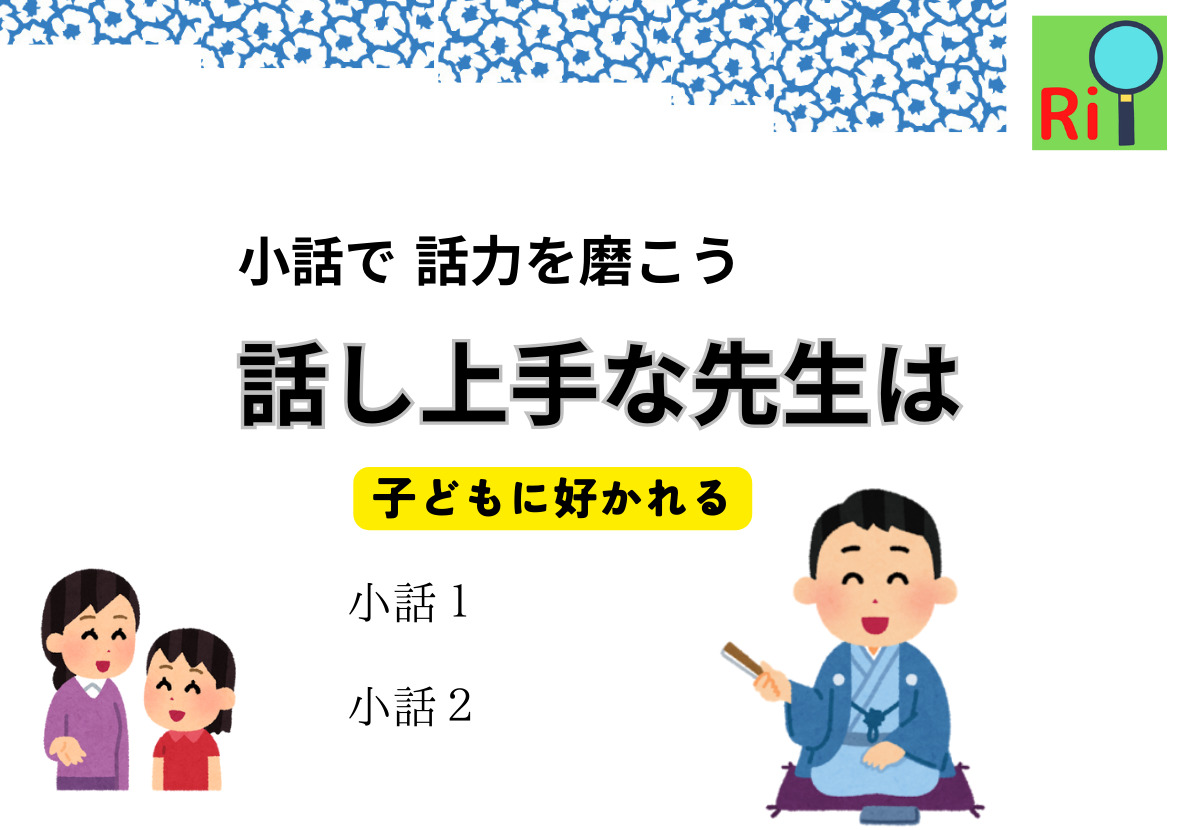「観察」とは どうすることなのか、分かっていません。
その都度教える必要があります。
子ども達の多くは、漫然と現象を見ています。
従って授業者は、
観察の方法、使う道具の扱い方、記録の仕方、安全面等の指導をしないといけません。
「観察」は理科の授業ではとても大切な学習活動の一つです。
「〇〇を観察しましょう。」と先生が言って、子ども達がねらいどおりに観察ができたらいいのですが、
それは一部の優れた子どもだけです。
以下に紹介する小話は、
授業に「観察」があるとき、「まくら」として話します。
新学期が始まって間もない頃がいいでしょう。
有田先生が講演会でされた話です。
ところで、
有田先生(故人)をご存じない方がいらっしゃると思います。
筑波大学付属小で社会科の授業を担当され、私も公開授業を幾度か参観。
NHKの教育番組制作にも携わっていらっしゃいました。
著書多数。
とりわけ「教育新書 〇年生に育てたい学習技能(明治図書)」からは多くの啓発を受けました。
尚、小話を収録した著作も出版されているようです。
理科授業でする小話のもう一つは、6年生の「大地のつくり」に関するものです。
こちらは、授業の隙間時間にされるといいかな、と思います。
1.「観察」に関する小話
ここは、大学病院。
医学生の指導にあたる先生が話をしています。


医者にとってよく見る、観察するということはとても大切なことなんだ。
これを見なさい。
うちに入院している患者さんのおしっこ、尿だ。
もう検査は終わっとるから捨てるものだが、お前たちの研修のためにとっておいた。
昔は、尿をこのようにして病状の診断をしたもんだ。
私がやってみせるから、よく見ておれよ。
そう言って先生は、小さなビーカーを学生一人一人に渡しました。
黄色い液体が少しずつ入っています。
まず、人差し指でゆっくりとかき回す。
しずくを払って、
指を口にもっていき、味をみる・・・さ、やってみろ。


「えー、舐めるんですか?」
「先生、ほんとにやるんですか?」
学生たち、少し嫌がってましたが観念したようです。
人差し指を黄色い液体中に突っ込むと、ためらいながらもその指を口に入れました。
先生、苦いです。
こんなことをして、どんな診断ができるんですか?
ぺっ、ぺっ、と吐き出しているところへ
お前たちは本当に舐めたのか?
よくそんなことができるなぁ、私にはできん。
だって、先生は、指を舐めましたよ。




お前たち、よく見ていなかっただろう。
わしは人差し指でかき回し、しずくを払ったが、
口に入れたのは隣の中指だ。
よく見ていないから苦い思いをする、そういうわけだ。
理科授業でする小話ですから、それなりに話をまとめて終わります。



「観察」とは、
注意深く見る事、と辞書に出ています。
「察」とは正しく想像し理解する、とあります。
みなさんも
自分の目でしっかりと現象をとらえ、考えていくようにしましょう。
2.単元名「大地のつくり」での小話
理科授業でする小話の二つ目。
6年理科で「大地のつくり」という単元があります。
浸食と堆積。
その繰り返しによって大地ができた、という授業での小話を紹介します。
このお話も有田先生によるものです。
繰返しになりますが、単元を指導中の、すきま時間にするのがおすすめ。
この小話から授業へつなげるのはちょっとムリな気がします。
地層が見られるグランドキャニオン



「グランドキャニオン」を知っていますか? (映像を出す)
写真を見せながら話をしていきます。
アメリカのアリゾナ州にある国立公園です。
全長約450km、深さ約1.6kmにわたる世界最大規模の峡谷です。
川や雨、雪による水の浸食を繰り返して現在の姿になったと言われています。
20億年分の地層からは化石も出てきます。
地球の歴史を知るうえでも重要な場所で、世界遺産に登録されています。
グランドキャニオン国立公園 特集【HIS海外現地オプショナルツアー】 (his-j.com)


ここは、立ち入り禁止などの柵などありません。
転落事故が起きたら、それは自己責任となります。
そこへ、
日本の人たちがツアー観光でやってきました。
みなさんこわごわ、そおーっと下を覗いたりしていました。
さて、出発の時刻となりました。
ガイドさんが乗客の数を確認していると・・・一人足りません。
まさか、落ちたんじゃ?
乗客のみんなで探すことになりました。
転落事故の発生
崖の下の方から声が聞こえてきました。
呼びかけると返事がありました。やっぱり転落してしまったのでした。
ところが、
うまい具合に岩に引っかかっって、窪みにいるというのです。
上からはその窪みは見えません。
乗客の一人が声をかけます。
自分で上がってこれますかぁ?
すぐに返事が返ってきました。
力が入らないんです。手も、足も骨折しているみたいで無理でーす。
ツアー客の一人がバスに積んであったロープを持ってきました。
助けに行くのも危険です。
一人が名案を思い付きました。
ロープを垂らして、それ咥えてもらって引っ張り上げようというのです。


やってみまーす。 歯は丈夫なんでーす。
と返事が来たので、頃合いをみて引っ張り始めました。


崖の上では、ロープを引っ張る人。
がんばれー、がんばれーと励ます人。
ようやくその人の頭が見えてきました。
ロープを必死に咥えています。
がんばれー!
もう少しで手が届く、正にそのときです。
大きな声で、
おい、大丈夫か! ケガはどうだ?
と声をかけた人がいました。
返事がありません。
黙ってちゃ分からん。 返事をしろ!
その人、返事をしなくちゃと思ったのでしょう、
だいじょうぶです、
と言おうとして口を開いた途端・・・
ロープの手ごたえが一気に軽くなりました。
男の人の姿が見えなくなりました。


3.熱いコーヒーが好き、と言っても100℃以上にはなりません。
理科授業でする小話の3つ目。
これは、我が家の話です。
4年生の理科、「ものの温度と堆積」の授業で使えるかもしれません。
先生の奥さんは、コーヒーが好きなんです。
インスタントコーヒーでお湯を注いで飲むんですが、
あつあつじゃないとダメ、というのでどーするかというと・・・





どーすると思いますか?
この投げ掛けに、子ども達はどんなアイデアを出してくれるでしょうか。
恐らく、沸騰したばかりの湯を使う、というでしょう。
うちの奥さんは、こうします。
沸騰している湯をカップに注ぐと、それを電子レンジに入れて
3分間加熱するのです。
チーン、となったら取り出しておいしそうに飲み始めますが、
なんか言いたくなりますよね?


豆知識をちょっと入れてみる
ここで穏やかな家庭の空気が、一変するかもしれない場面が訪れます。
黙って見ていられません。
なぜだかわかりますか?



水は、いくら熱しても100℃以上にはならないんです。
沸騰したお湯、
つまり100℃近いお湯でコーヒーを入れてますから、
それから3分間レンジで加熱しても、コーヒーの温度は大して変わらないんです。
電気がムダなだけ。
ちなみに、
電子レンジで加熱できるのは水分で、入れ物自体は温かくなりません。
金属を入れるのは危険ですよ。火花が出ることがあるそうです。
必ずレンジ用の容器を使いましょう。
ところで・・・
奥さんに何て言えばいいのか、悩みますよ。
うっかり、
4年生の理科で習うことなんだけどね、
などといったら、もう口を利いてくれなくなりますからね。
奥さんとの人間関係が熱くならないように気をつけて話をします。


熱いのを飲みたいのは、よく分かるけどね、
70度を超える食べ物を食べたり飲んだりすると口の中を火傷するらしいよ。
そうそう、
水は100℃以上にはならないんだったよね。
ブラックでなく、クリームを入れるように
豆知識をちょっと入れるとマイルドになるかもしれません。
関連記事