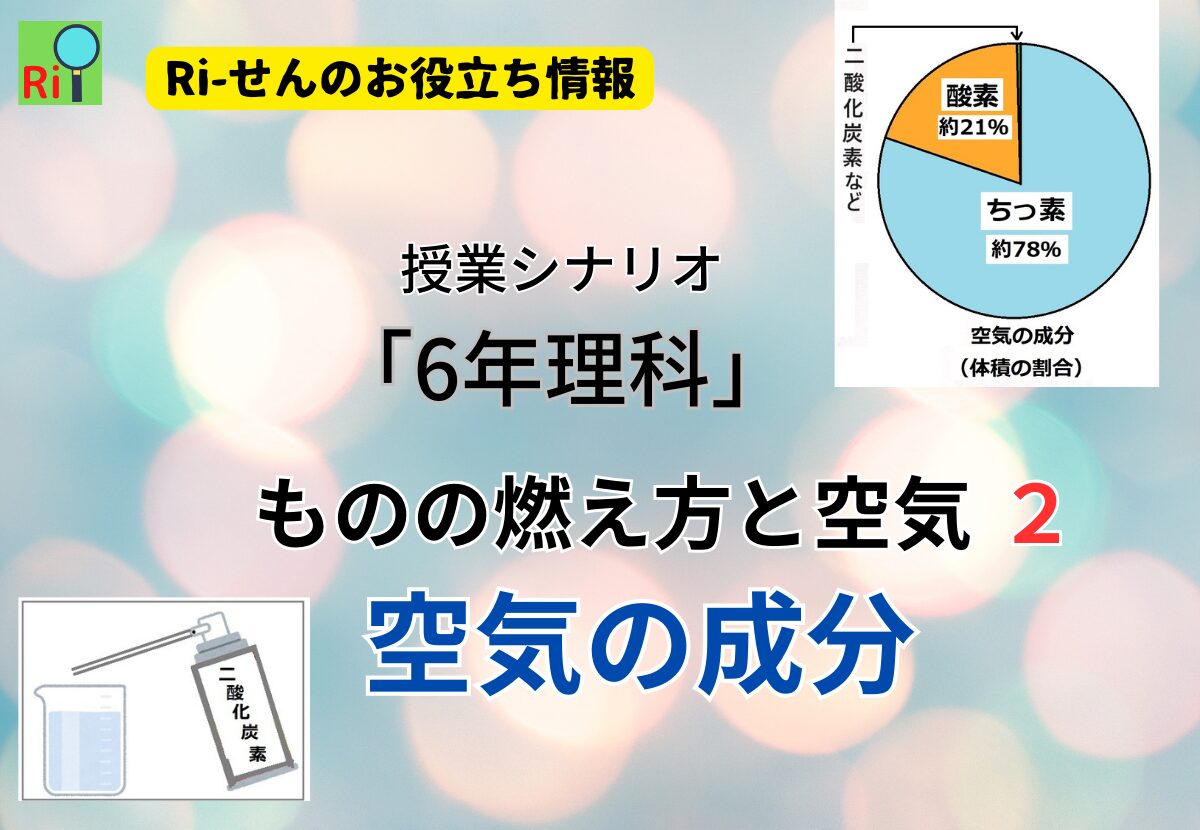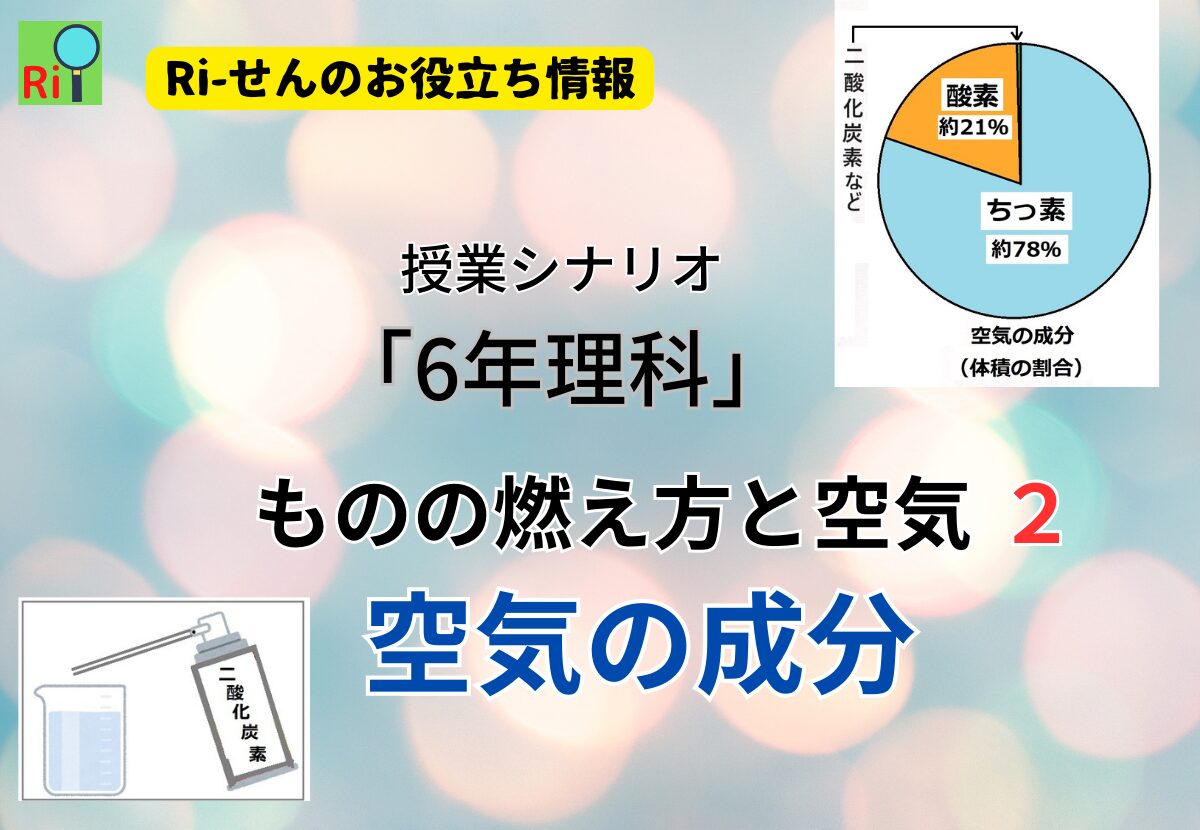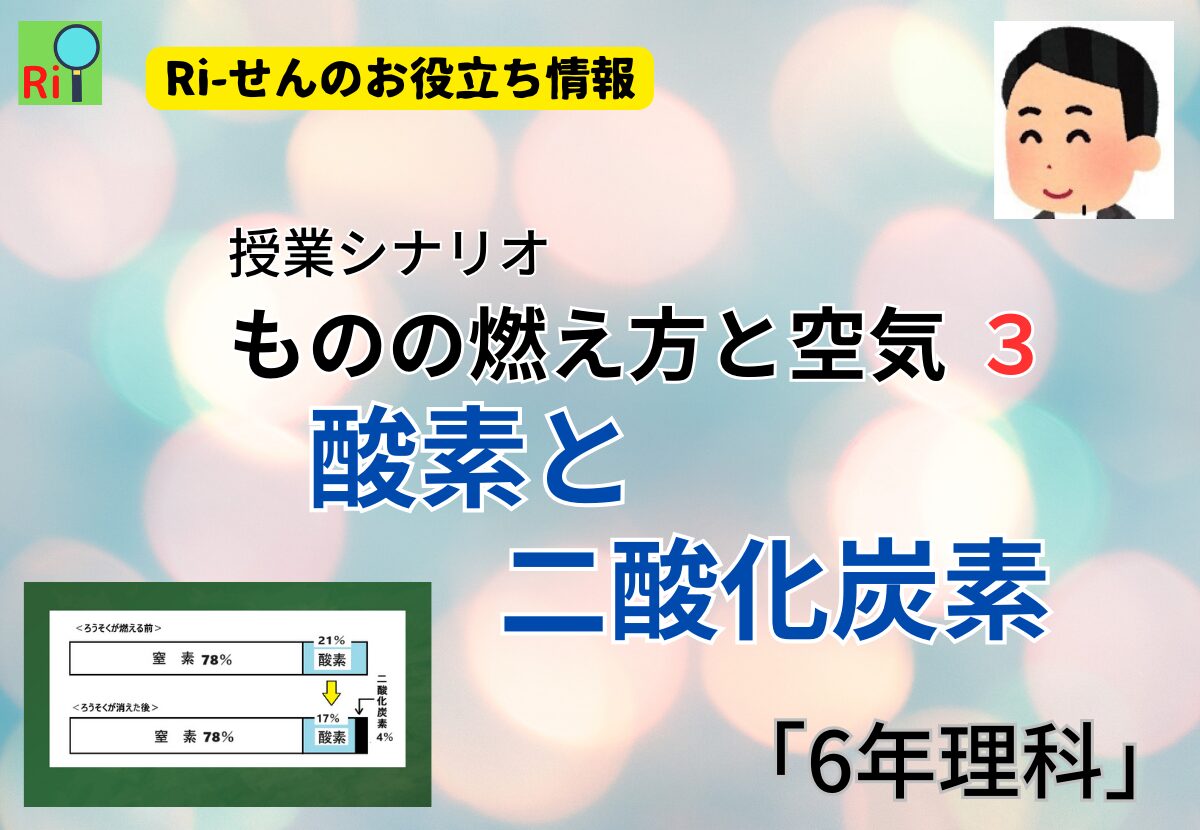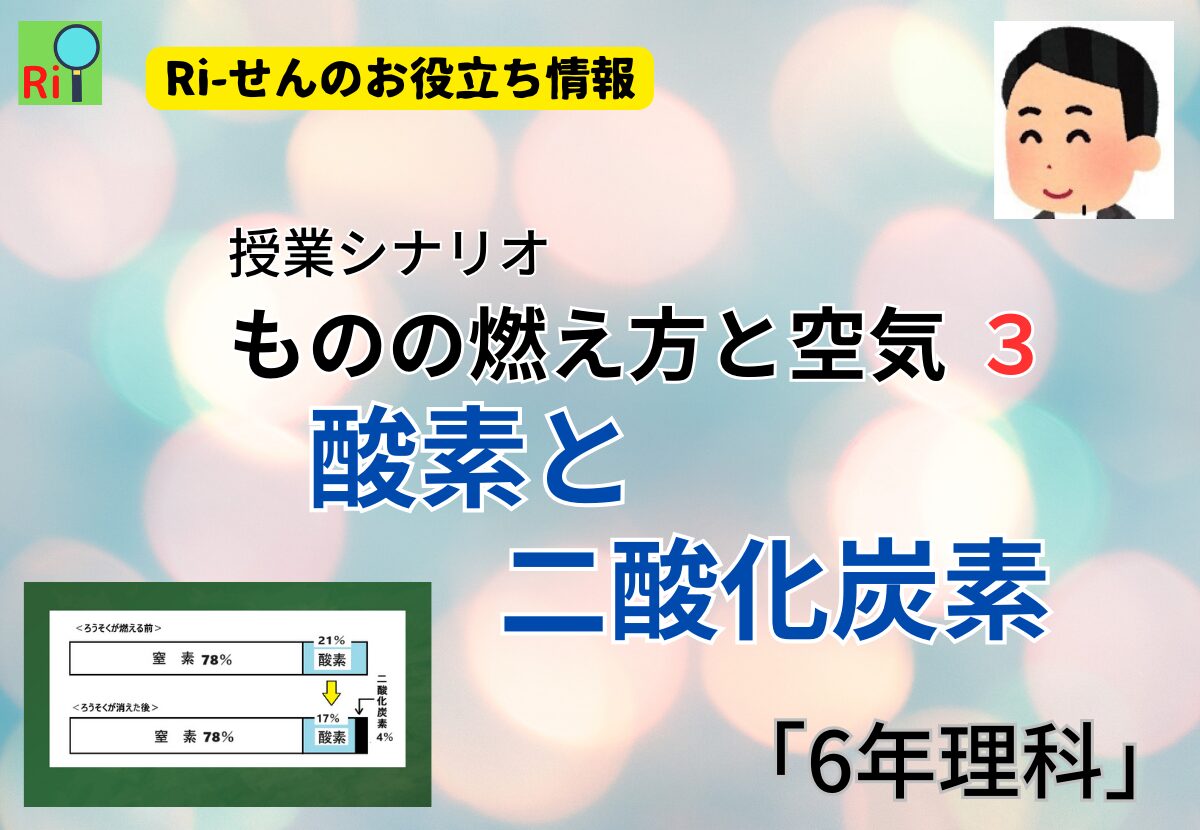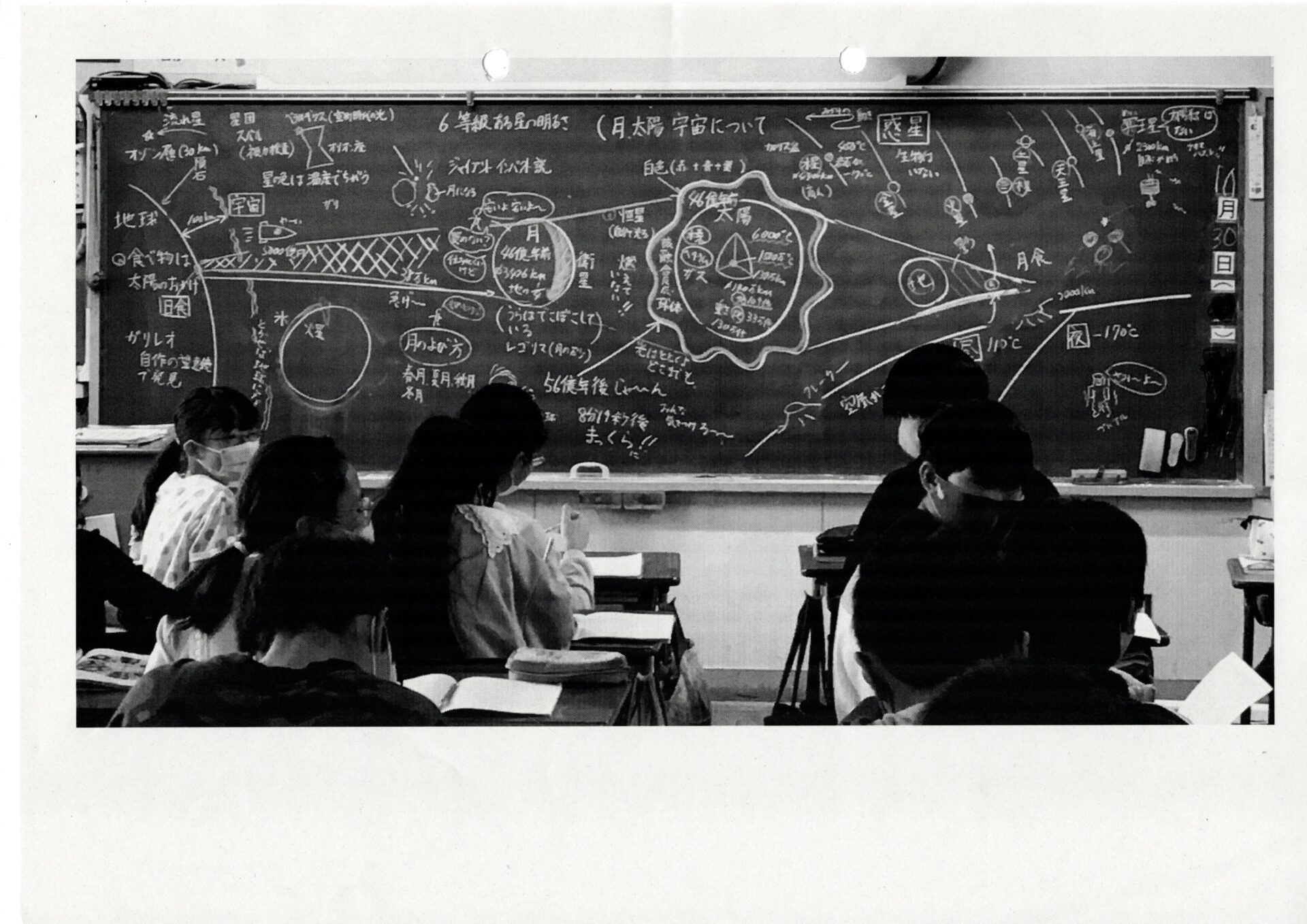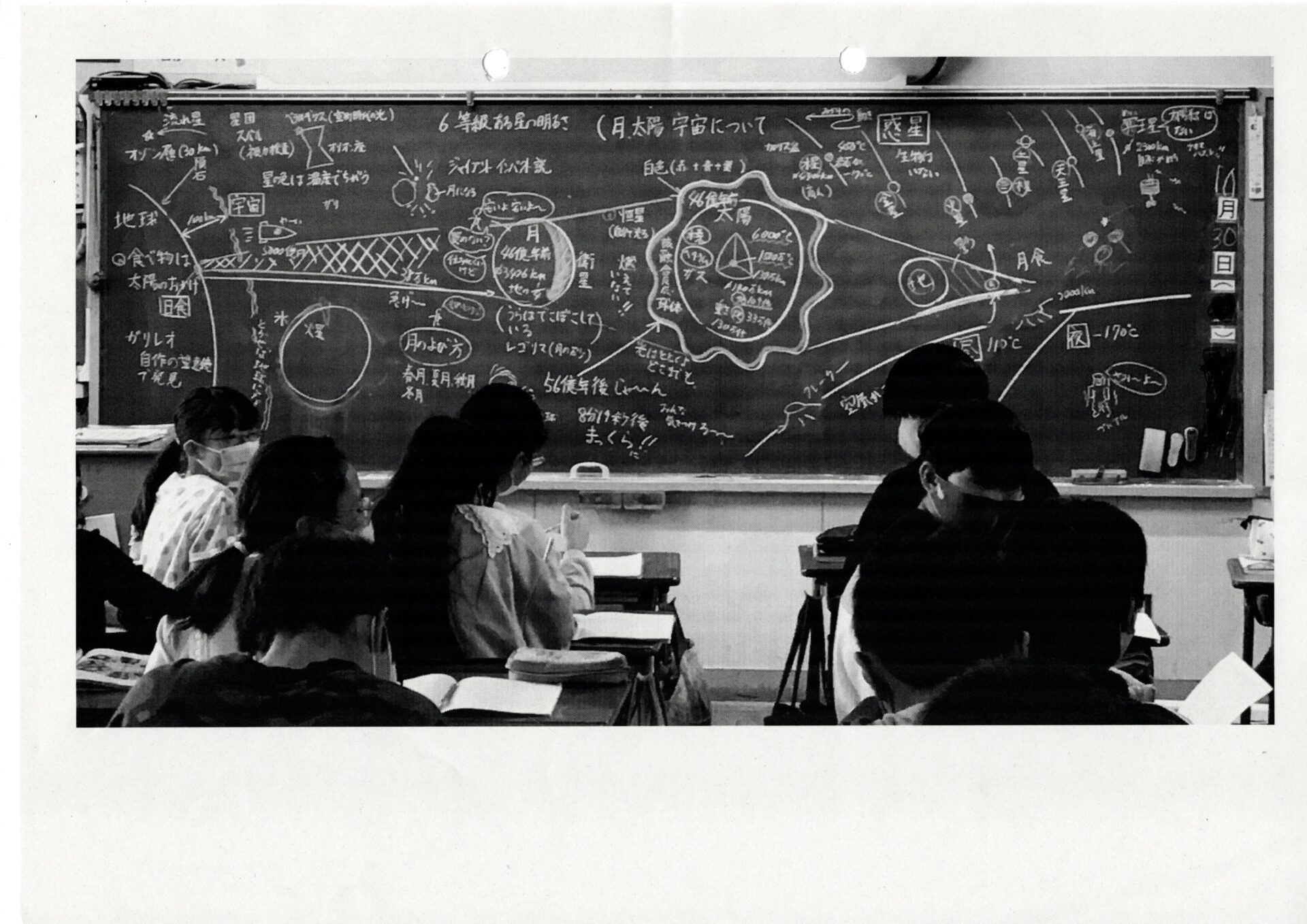「ものの燃え方と空気」 第1時の授業シナリオです。
現場のお役に立てたら幸いです。
はじめに
コロナ禍(下)の時期に行った授業を元に、記事を書き起こしました。
当時(2020年)は、
実験はしない・話し合い活動は5分以内等の制限がありました。
自ずと教師主導の展開となりました。
が、実験はしないわけにはいきません。
授業が楽しいものとならないからです。ガイドラインに沿った形で行いました。
1.授業の始まり
2.ふたをすると?
3.現象を表現させる
4.消えたのは、空気がなくなったから?
5.実験
7.マッチを使う (マッチで大会) →Jump there.
8.実験の前に
9.安全面等の話 (年度初めに注意)
1.授業の始まり(器具の名前を問う)
集気びんを提示するところから始まります。
器具の名称を問います。
T:何という器具でしょうか。
間髪を入れず、列指名していきます。
C:分かりません。
C:知りません、初めて見ます。
などと返ってくるので、ヒントを出します。





教科書を開いている人は、答えられますよねぇ。
教科書を見てごらん、という意味です。
子ども達は、教科書を「見て答えてはいけないもの」と思っています。
そんなことはありません。
見ていいんです。
授業を受けるときの心構えをそれとなく指導しているわけです。
ぱらぱらと頁をめくり出す子ども達。
ありました。準備物としてP8に書かれているのでした。
同様に、
燃焼さじ、マッチ、燃えさし入れの現物を見せて名称を言わせていきます。
理科では、実験器具とその名称をおさえることも大切です。
ちなみに、
ここは理科室ではありません。
事前に教室に運んでおき、廊下に置いておきました。
2.ふたをすると?
名称を確認したところで、授業の中身に入っていきます。
ろうそくを取り出し、マッチで火を点けました。
子ども達は先生のしていることをじっと見ています。
そのろうそくを集気びんまで近づけてストップ。
ここで投げかけます。



ろうそくをびんに入れてふたをすると、火はどうなるでしょうか。
つぶやきが聞こえます。
「消える」とか「しばらく燃えてる」とか。
いい反応です。
T: まずは、問題と図をノートに書きましょうか。
と言って板書を始めます。
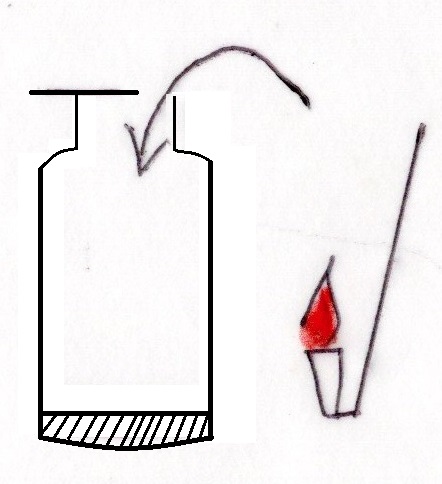
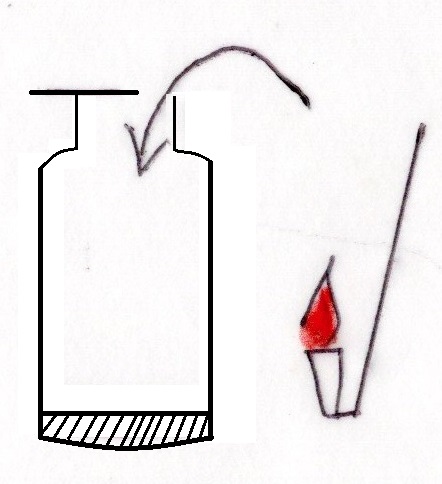
図には、説明を入れます。
・水を1cmの高さに入れる
・燃焼さじは、集気びんのまん中に置く
まだ黒板を写している子どももいますが、構わず投げかけます。
T:予想も書けましたよね?
顔を上げているのは、たぶん書き終わっている子どもです。
その数人に当てていくと「消えます」と返ってきました。
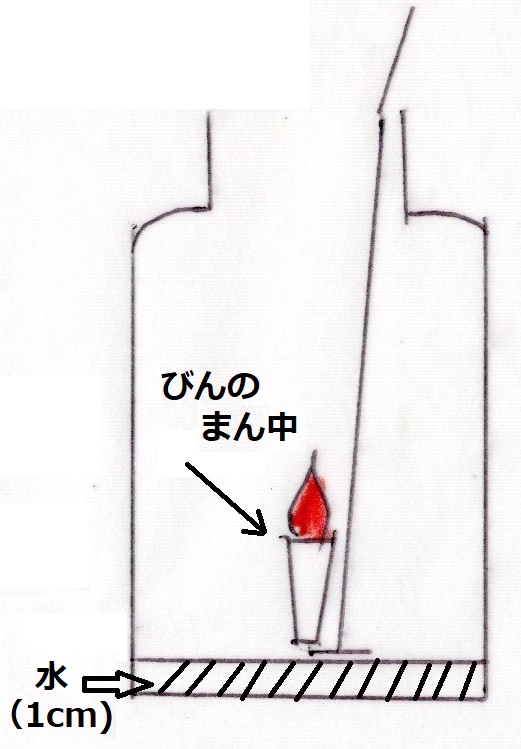
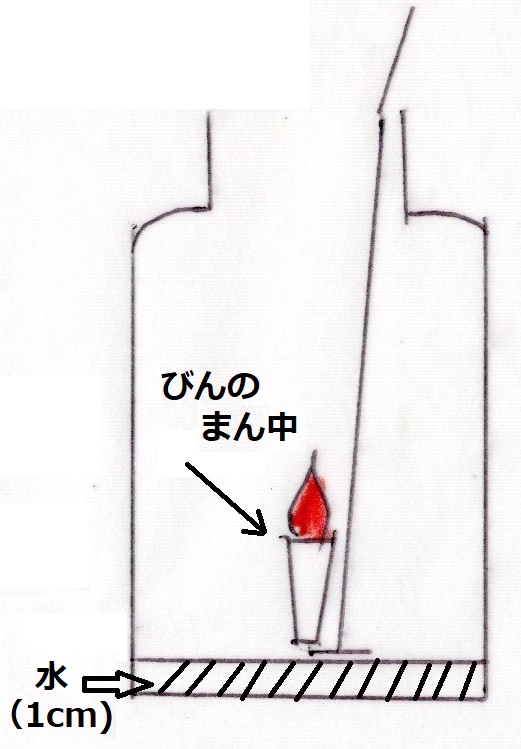
ふたをすると消える、その理由を言ってもらいます。
空気がなくなるからとのことでした。
空気が悪くなるから、というのもありました。
そう考えた説明を求めることもできますが、
今は止めときます。(時間がありません。)
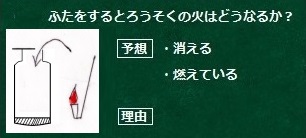
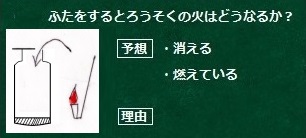
「消える」ということに、まず突っ込みを入れます。



ふたをすると「消える」ということですが、
すぐ消えると思います? それとも1分ぐらいしてからかな?
子ども達は、そこまでは考えていません。
じゃやってみましょうか、と演示に移ります。
3.現象を表現させる
蓋をすると、
炎は次第に小さくなって10秒ほどで消えてしまいました。
その様子をノートに記録しておくように指示します。
列指名し、ノートに書いたとおりに読んでもらうと
どの子も「消えた」とか「消える」と返してきました。
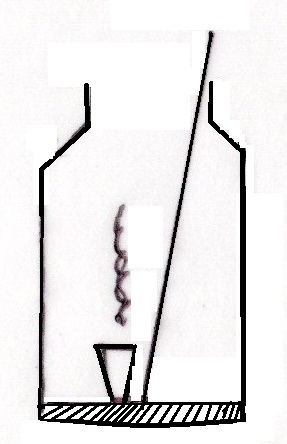
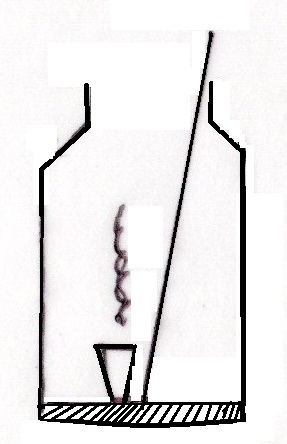


何とシンプル。
たったの3文字です。
そういう表現を放置していていいのでしょうか?
ここは指導の場面です。
もう少し長めに表現してほしいなぁ、というと
C:だんだん炎が小さくなって消えた。 とか
C:10秒くらいしてから弱くなって消えた。
とか返ってきました。
少し詳しい表現になりました。



では、もう一度やってみましょう。同じように消えるでしょうか。
一瞬でした。
ろうそくを集気びんに入れた途端、火が消えました。
予想外だったらしく、びっくりしている子がいます。
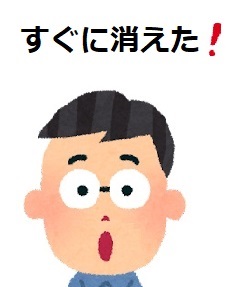
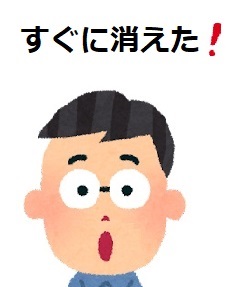



あれっ? て思いましたよね。
疑問が湧きましたよね? 言ってみてください。



すぐに消えたのは、もう空気がなくなっていたからだと思います。



一度燃えているのでびんの中の空気が古くなっているんだよ。
新しいびんでやらないと同じ結果にはならないんじゃないかな。
4.空気がなくなったから?
火が消えたのは、空気がなくなったからだ。
その発言から授業を進めていきます。



空気がなくなった、という発言がありましたね。
空気がない、というのはどういう状態でしょうか。
真空っていうこと?
そんなつぶやき声が聞こえました。
「空気がない」は「真空」といっていいのでしょうか。
いいのです。
調べてみると、「大気圧より低い圧力の空間を真空と呼ぶ」そうです。 空気がない状態 – Google 検索
これをおさえます。



皆さんは真空を作ったことがありますよね。
3年生の理科で空気鉄砲で遊んだことあるでしょう。
と言いつつ、取り出して見せます。
真空状態をつくります。
先端を指で塞ぎ、
取っ手を引いていくと、空間が現われます。
T:これが、空気がない状態。 真空です。
引っ張るのをやめると取っ手は戻り、空間はなくなりました。
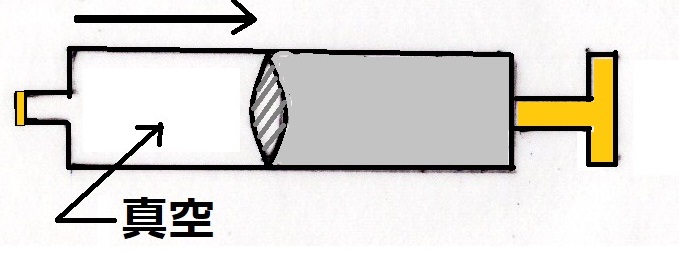
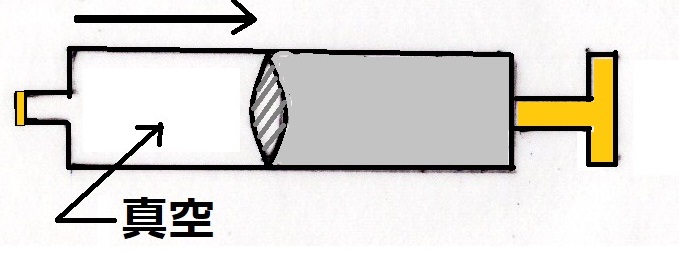
火が消えた後の集気びんはどうだったでしょうか。
空気がなくなったようにはなっていません。
ダメ押しです。
やって見せてしまいます。
水中で蓋をとると、ぶくぶくと泡が出てきました。
泡は、空気です。
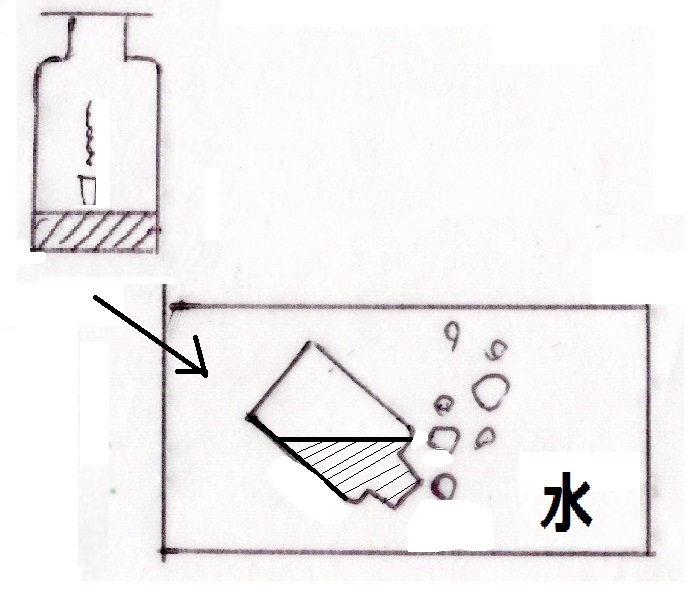
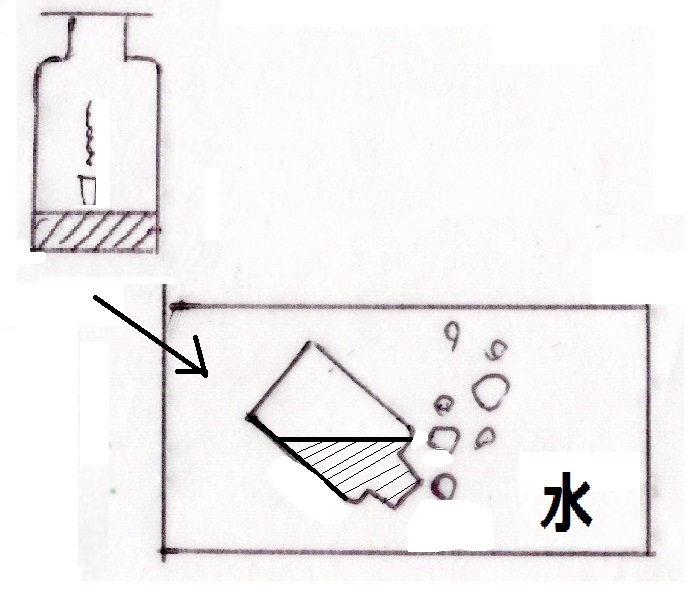
集気びんの中に空気があることがはっきりしました。
その空気の中ではろうそくは燃えませんでした。
もう、燃やすはたらきはない、ということです。
ここまでの学びをまとめとしてノートに書かせ授業を閉じました。
5.実験
コロナ禍であっても、実験はしました。
自らがモノに働きかけて学ぶ。
目の前で起きる現象を見ること、感じることを理科の授業では保障したいと思いました。
実験の映像を観せてそれで指導を終える訳にはいきません。
子ども達は、びんの中で火が消える様子を演示で見ただけです。
結果は分かっていますが、実際に子ども達にさせていきます。
可能な限り、一人(若しくは二人組)で進められるように用具の準備をしました。
集気びん20個、燃焼さじ20本のほか、マッチ等の20セット用意しました。
6.マッチを使う
まず、マッチの指導をします。
学校にはライターもありますが、敢えてマッチを使います。
擦ると着火する。
これを体験させたいと思います。


子ども達は、擦る時にマッチを折ってしまいます。
炎が指に近くなってきて、火の点いているマッチを放ってしまうことも、します。
これは、軸木の持ち方が分からないためです。
頭薬の近くを指3本でつまみます。
擦って着火したら、炎を上向きにします。
中指を離して親指と人差指の2本でつまみます。
消えそうになったら、
手首を返しながら軸木を傾けて、火をもたせます。
これを目の前でやってみせます。
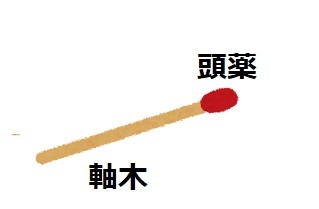
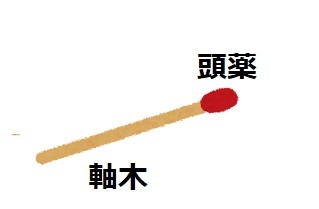
マッチを擦る練習をして慣れたところで、ゲームをします。
「誰が一番火をもたせられるかゲーム」です。
軸木をつまんでいる部分をぎりぎり端まで移動させていくと
30秒は持たせることができます。
ちなみに、
マッチ箱に「安全マッチ」と書かれています。
「安全」とは自然発火の危険がないという意味です。
西部劇の映画などを見ていると、ブーツの底でマッチを擦っているシーンがありました。
あれは、安全マッチではありません。
マッチの詳細については こちら マッチの歴史 | JTウェブサイト (jti.co.jp)
7.実験の前に
週が改まりました。
子ども達の頭の中はりっかりとリセットされています。
先週は何したんだっけ、状態になっているので授業は確認から始めます。
右図を提示して、投げかけます。



これ(図)は、何を確かめる実験ですか?



ふたをするとろうそくの火はどうなるか、です。
消えた後に再び火の点いたろうそくを入れてみることもします。
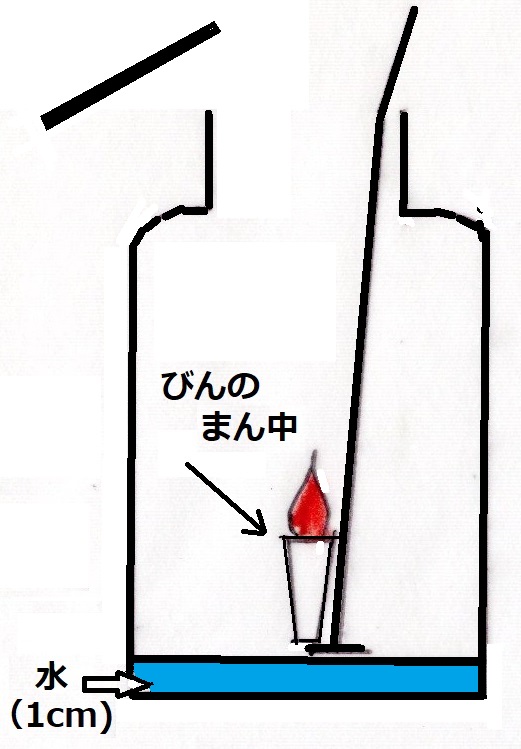
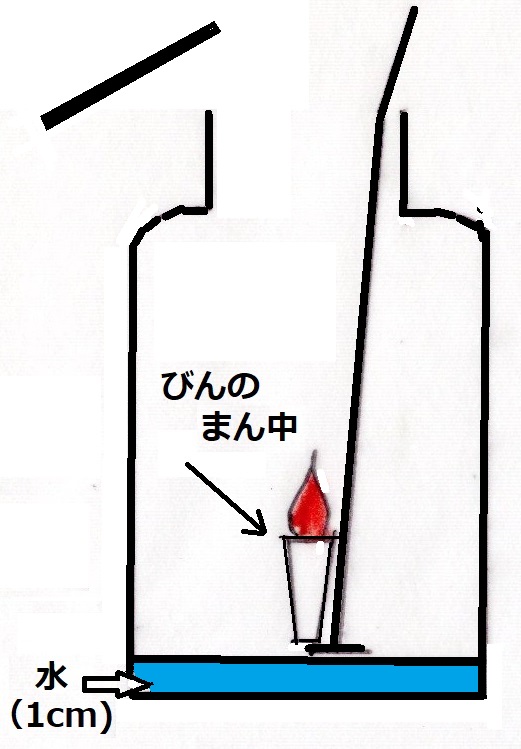
実験の仕方については細々(こまごま)あり、話しておきます。
- 机のまん中で実験を行う。
- 教科書、ノートは片付けておく。
- ろうそくは、びんのまん中に置く。
- 濡れぞうきんを用意。
- 燃えさし入れには水を少し入れておく。
- 実験は2回する。同じ結果となるか、確かめる。
8.安全面等も
6年に進級し、
初めての理科実験ですので、こんな話もしておきます。



お互いに注意し合って安全に実験をしてください。
学校の物は大切に扱うこと。壊れたら正直に申し出ること。
誰でも不注意はあります。それを叱ることはありません。
いたずら等、面白半分に目的外のことをした場合はイエローカードです。
その場合は、実験への参加はできなくなります。
※実験後の授業については割愛します。
関連記事