離任式で何を話すか。
学校職員なら周知のことですが、
異動となると、離任式でお別れの挨拶をすることになります。
ちょっと悩みますよね。どんな話をしたらいいのか、と。
そんなときのご参考になれば幸いです。
1.はじめに(登壇者の多くは「話」を準備していない?)
2.離任式も「授業」です → Jump there
3.記憶に残る「離任者の話」 うんとやさしい人になれ → Jump there
4.私の「離任の話」 → Jump there
1.はじめに (話を準備して臨みましょう!)
離任者に対して大変失礼な話ですが、つまらない話が多いです。
それが正直な私の感想です。
儀式だから子ども達は緊張感をもってじっとしていますが、
聞かされているその時間が気の毒になってくるほど中身のない話です。


この節は、
転出職員が5人も6人もいて、そのため離任式が1時間近くにも及びます。
子ども達は、その間ずっと立っています。どんな思いで聞いているのでしょうか。
一方の離任者。
在職中のあれこれを思い付くままにしゃべり続けます。
3分くらいするとネタがつきたのか、もう気持ちが満たされたらしく、まとめにはいります。
次の方も同じ。
どの方々もそのパターンです。(ホントに御免なさい。離任する先生方!)
どうしてそうなってしまうのか?
話を準備してきていないからだと思われます。
離任式も、授業であることを認識していないからだと思われます。
2.儀式も「授業」です
儀式的行事も「授業のひとつ」です。
そのように捉えていないから準備をしないのかもしれません。
子ども達にとって学びとなるような、
これを伝えたい、という思いが感じられるような、
メッセージを込めた話を準備して、式に臨むようにしたらよいのでは、と私は思います。
念のためにお断りしておきますが、その先生らしさを否定するものではありません。
その教員と関係がある子ども達にとっては、
他者には分からない特別な景色が浮かんでくる時間になっているのかもしれません。
ただ、それは一部。大多数の児童にとっては縁のなかった「知らない先生」です。
記憶を辿れば、すばらしいご挨拶をされた方も少なからずいらっしゃって、
別れが一層切なくなった思い出もあります。
その先生から、別れの挨拶はかくあるべしと教えられたようにも思います。
様々な機会を経て、
様々な子ども達や様々な先生と出会って教員は成長します。
次はこうしてみよう、と考えるものです。
それは授業づくりと同じです。
3.うんとやさしい人になれ
さる教頭先生の挨拶は、今も印象強く心に残っています。



勉強が好きな子は、いっぱい勉強しなさい。
運動が好きな子は、もっと運動を得意になりなさい。
勉強も、運動も苦手な子は・・・うんとやさしい人になりなさい。
では皆さん、さようなら。
それだけ話すと、降壇されました。
あっという間。
多くを語らず、実にシンプルでしたが、心にじんと響くものがありました。
長きにわたる教職経験から絞って絞って抽出したような、子ども達へのメッセージだと思いました。
4.私の「離任式での話」
私の場合を紹介します。
まず、この時間を一つの「授業」の場と捉えました。
名前が呼ばれたので演台に進みます。
一礼して、こんな話で始めました。



神様がおりました。
そこに、ウサギが通りかかりますと、神様が声を掛けます。
これこれ、ウサギ!
お前には牙もなければ鋭い爪もない。
だから、一つ優れたもの「飛ぶように走れる足」をやろう。
そう言って神様はウサギの足をなでました。
ウサギは不思議そうな顔をしてお辞儀をすると、
ぴょんぴょーんと飛ぶようにして行ってしまいました。


その様子をじーっと見ていたのがキツネです。
急いで神様のところにやってきました。
神様、神様!
今、ウサギさんにあげた「飛ぶよう に走れる足」。
あれ、ぼくにもください。
すると神様は、あきれたように言いました。


おいおいキツネ!
お前にはさっき「かしこい頭」をやっただろう。
優れたものは一人に一つ。
二つ欲しいなんて、お前は欲張りなヤツだなぁ。
子ども達に問う
ここで、子ども達に問いかけました。



皆さんは、
キツネの言うことに賛成ですか? 神様の言うことに賛成ですか?
「もう一つくれ」と言ったキツネに賛成の人!
と問うと、
手を挙げる子はほとんどいませんでした。ぱらぱらといった程度。
どうしてキツネなんかに賛成なんだよ、という目で後方を振り返っている子もいます。
次に「神様に賛成の人」を聞くと、
わーっと手が挙がりました。当然だとでも言うように。
天井に突き刺さるような手の挙げ方は、自分の判断の正しさを誇示するかのようです。
しめしめです。
想定通りの反応をしてくれました。
先生は・・・
ここからが、話の核心です。



先生は、キツネの言うことに賛成です。
子ども達の顔つきが変わりました。
えっ、何で?
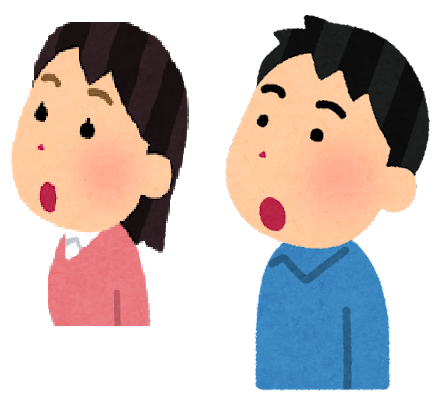
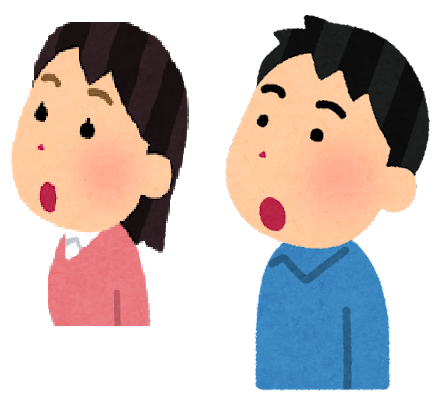



だって、
先生はかしこい頭も欲しいし、速く走れる足も欲しいです。
「優れたもの」は
一人に1つじゃなくて、いくつもあったっていいじゃないですか。
しめくくる



「優れたもの」は、いくつもあったらいいですよ。
いろんなことができますから。
話を続けます。
でも、「優れたもの」は、誰かからもらえるものではありません。
自分でがんばって身につけていくものです。
「優れたもの」は勉強や運動のことだけではありません。
人と仲良くできたりするのも、みんなの役に立つことを進んでしたりするのも、
すばらしい力だと先生は、思います。



みなさん、
そういう「優れたもの」をたくさん身につけていってください。
それでは、お元気で。 さようなら。
この話は、職員にも印象深く受け止められたようです。
歓送迎会で話題になりました。
参考になったのだとしたら、うれしいかぎりです。
その準備
離任式での話をどうするか。
子ども達の心に響くような話をしたいわけです。
参考になりそうな本を書架からピックアップし、机に積み上げました。
それらを1冊ずつぱらぱらと見ていくうちに、使えそうな話が思い出されてきました。
この記事の話は元があります。
向山洋一氏の著書の中のエピソードで、氏の勤務校の校長先生が朝会でされた話です。
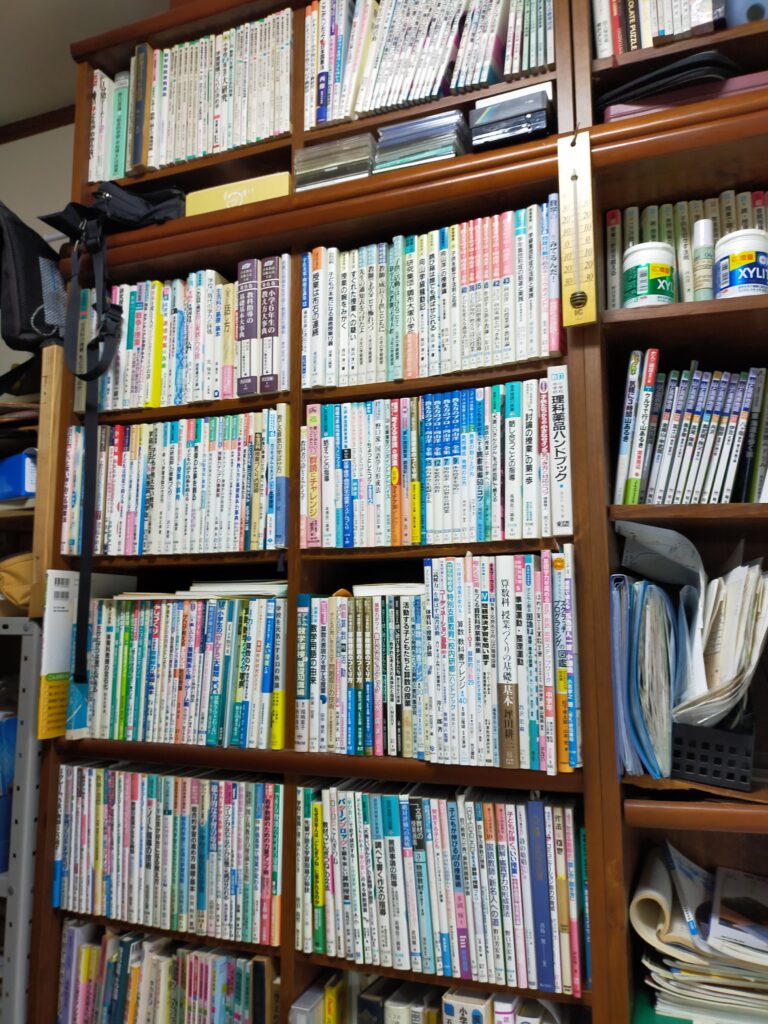
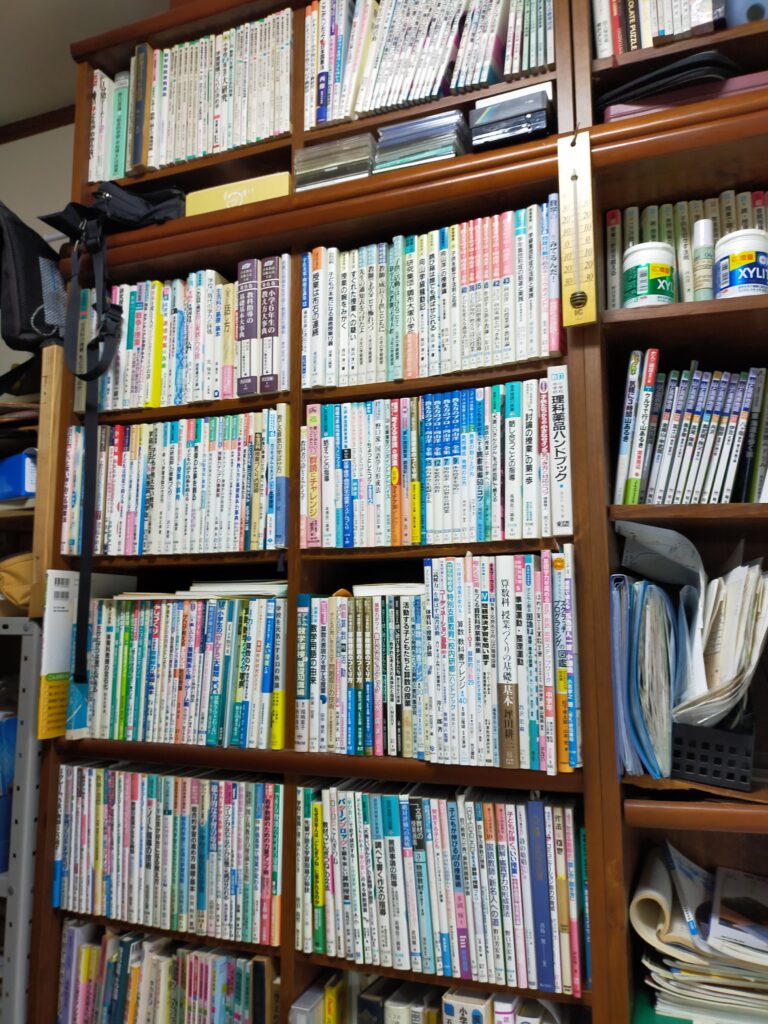
それをベースに多少の脚色をして組み立てました。
何度か練習をして、離任式に臨みました。
☆現職の先生方のお役に立てたらと、これからも情報発信をしていきます。

